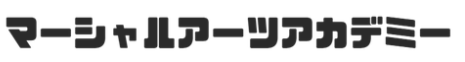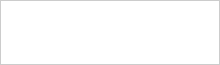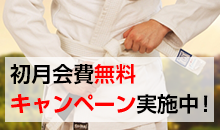柔術クラスの高津です。
僕のピアノの師匠の生徒さんで、すごくフリーダムに演奏する子がいるそうです。
それがまたいい音を鳴らすらしいのですが、やってるのはクラシック。音階や拍子、強弱記号で定められた基本的な演奏技術を学ぶことが大事。
しかしながら個性的な感性を抑圧してしまってももったいない。
なかなか悩みどころだと思います。
守破離
芸事や武道の修業段階について言われることに「守・破・離」があります。
最初は教えをそのまま型通り”守り”、修練する。
次第に教えを受けた型を”破って”、自分なりの工夫を重ねていく。
ついには既存の型から”離れて”、独自の境地に至る。
現代社会において、古い型にハメるということは自由な発想を抑圧し、多様性を消し去り、発展から遠ざかる活動に思われるかもしれません。
しかし多様性とは少なくとも”破”の段階、創造性に至っては”離”の領域だと思います。
基本や土台が無いのに自由にやっても、個人の才能分の成果しか生み出せません。
人類がこれまでやってきた蓄積に関する理解の上に、自分の才能を上乗せして更新していくことが発展や進歩と言えるのではないでしょうか。
”守”つまり”型”には、偉大なる先人たちの膨大なるトライ&エラーに磨き上げられて残ったエッセンスが詰まっています。
武術では「初伝と奧伝は同質」「基本こそ極意」と言いますが、まさにそういうことですよね。
具体的なフレームとしての”型”を感覚を研ぎ澄まして稽古していくうちに、抽象的で本質的な”形”が身についていく。
そこにある「様式美」は、停滞的で抑圧的なイメージとは程遠い、洗練されたものへの美意識です。
そこに到達するためには、何かと自由や個性を強調される世風ですが、まずは武道や芸能がやってきたように、先達の教えを守って”型”を修練するのが大事だと、僕は思います。
投稿者プロフィール
最新記事一覧
 ブログ2019年5月30日昇級!~成長が目に見える喜び~
ブログ2019年5月30日昇級!~成長が目に見える喜び~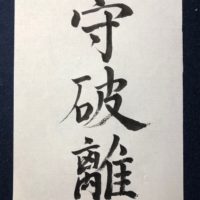 ブログ2019年4月18日守破離~自由な時代だからこそ、大事な型!そして形へ・・・
ブログ2019年4月18日守破離~自由な時代だからこそ、大事な型!そして形へ・・・ ブログ2019年3月18日「打撃と音楽」
ブログ2019年3月18日「打撃と音楽」 ブログ2019年2月25日第32回京都府柔道選手権大会に出場しました
ブログ2019年2月25日第32回京都府柔道選手権大会に出場しました